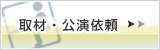特殊清掃を扱う専門会社「特殊清掃24時」:特殊清掃「戦う男たち」2007年分
特殊清掃「戦う男たち」
野良猫
私は、自分で、〝世渡り上手〟とまではいかなくても、〝世渡り下手〟だとも思っていない。
ま、どちらにしろ、人との付き合いが下手クソなのは事実。
仕事関係なら、それなりの必要事項を喋っていれば済むけど、そうでない相手とは何を話せばいいのか分からなくて困る。
私は、機転のきいた社交辞令的なネタを、まず思いつかない!
だから、初対面の人や関わりの薄い人と時間を消化しなければならない場面はツラくて仕方がない。
人間関係って楽しいこともあるけど、疲れることも多い。
本音と建前の使い分けなんて考えてしまうと、すぐさま人間不信に陥る。
普段は一人でいる方が楽なのに、何かあると一人では心細い。
孤独を愛する淋しがりやの私は、犬のように人になつくとこもできず、猫のようにマイペースにもなりきれないのである。
猫って、街のどこにでもいる。
都内でも郊外でも、どこででも見かける。
街の表裏をうろつく野良猫は、私には世渡りが上手い動物に映る。
現場は小さな一戸建、故人は老年の女性。
玄関を開けるとすぐに不快な猫臭を鼻に感じた。
と同時に、部屋の中に何匹もの猫がいるのが見えた。
「猫・・・屋敷?」
失礼ながら、玄関から垣間見える家の中はかなり不衛生な状態で、あちこちに猫の毛とトイレ用の砂が飛散・散乱。
更には、猫特有の異臭が充満。
しかし、〝慣れ〟というものは恐いもので、遺族の中年女性はそんなことも全く意に介してない様子で、
「遠慮なくどうぞ」
と、私を中に招き入れた。
また、そのエプロン姿とあっけらかんとした物腰は、遺体が安置されている家の人であることを感じさせない雰囲気も醸し出していた。
「失礼しま~す」
私は、あまりの汚さに躊躇いながらも靴を脱ぎ、足元にまとわりついてくる猫を避けながら玄関を奥へと進んだ。
家の中を見渡すと、壁には何枚もの猫の写真やポスターが貼ってあり、猫の写真が入った写真立ても並んでいた。
故人が一緒に写ったものも多く、そこからは故人が根っからの猫好きであったことが伝わってきた。
「随分と猫がお好きだったんですね」
「ええ・・・でも、父が亡くなって独りになってからなんですよ」
「へぇ~、そーなんですかぁ」
「それまでは、動物なんて飼ったこともなくてね」
その女性は、故人の娘だった。
そして、故人が猫好きになった経緯を懐かしげに話してくれた。
この猫達は、もともとはこの家の回りに住み着いていた野良猫らしかった。
夫を亡くして独り暮らしになった故人は、それを野良飼い。
余計な束縛も干渉もなく、都合のいいときだけの付き合いで済むので、お互いにとって心地よい関係だっただろう。
しかし、そんな中途半端な飼い方を近所の住人達は問題視。
多くなってきた近隣からの苦情をかわすため、故人は猫達を家の中に入れペットにしたのであった。
独りでは埋められない心の穴を、猫との関わりで埋めていたのだろうか。
故人が安置されている部屋に入ると、私は、いつものように遺体の傍らに正座し、顔の面布をとった。
そこには、安らかな表情の老年女性がいた。
この故人に限ったことではないが、老年の遺体の顔に刻まれるシワと安らかな寝顔には、こっちもホッとするような何かがある。
生老病死の摂理に逆らわず人生を終えていくことに、何とも言えない安心感?みたいなものを覚えるのだ。
いつもなら、死体業者の目をもってマジマジと顔を見るのだが、このときは何匹もの猫が歩き回っていて落ち着いて見ることができなかった。
猫は、故人の回りを歩き回ったり故人の布団に乗って寝転がったりするだけに留まらず、私にまでちょっかいをだしてきた。
私の身体に頭を擦りつけたり、膝に乗ってきたりと。
女性は、その都度、猫を捕まえてくれるのだが、どこかに閉じ込めるわけでもないので、すぐに戻ってくる。
それを気にしてても仕事にならないので、私は猫を無視して作業を進めることにした。
しばし後、故人を柩に納める支度ができた頃、女性が私に声を掛けてきた。
「こんなとこ写真に撮る人います?
「写真ですか?」
「ええ・・・」
「多くはありませんけど、写真を撮られる方はいらっしゃいますよ」
「撮っても問題ないですよね?」
「ご自由になさっていいと思いますよ」
「じゃ、せっかくだから撮っちゃお」
始めからそのつもりだったのだろう、女性はエプロンのポケットからデジカメを取り出した。
そして、レンズを故人の方へ向けた。
その視界には、猫も入っていた。
おまけに私も。
「私は入れないで(撮らないで)下さい!」
と、正直言いたいところだったが、女性の想いに水を差すことが目に見えていたので、渋々諦めて我慢。
まるで何かの記念撮影でもするかのように、女性は、立ち位置を変えながら次々とシャッターを押していった。
そんな女性も、故人を柩に納めるときはさすがに消沈。
悲しそうに涙を流した。
エプロンで何度も涙を拭う姿が悲哀を誘った。
そんな中、
「ちょっと待ってて下さい・・・お棺に入れたいものがあるんで」
と、おもむろに言い残して、女性は部屋を出て行った。
部屋には、柩と猫と私だけがポツンと残された。
そこは、誰も何も喋らない静かな空間。
人がいないと妙に落ち着く私は、柩の中に眠る故人と傍にたたずむ猫達を眺めながら、色んな思いを巡らせた。
「また一人、この世を去った・・・どんな人生だったんだろうな」
「これから、この猫達はどうやって生きていくんだろう・・・また、野良に逆戻りかな」
しばらくすると女性が戻ってきた。
撮りたての画像をプリントアウトしてきたらしく、手に何枚もの写真を持って。
「お母さん、猫ちゃん達の写真を入れとくからね」
そう言いながら、女性は故人の顔や手の回りにできたての写真を置いていった。
「やっぱり・・・俺も写っちゃってるじゃん・・・」
案の定、その中の何枚かの写真には、バッチリと私の姿があった。
「なんか、気持ちよくないなぁ」
〝魂が抜ける〟とか〝故人に連れて行かれる〟なんて迷信は信じてはいないけど、自分が写った写真を故人の柩に入れられることに、本能的な?抵抗感を覚える私だった。
(この醜態は、到底、もったいつけるレベルにはないんだけどね。)
「さようなら、お母さん・・・元気にやっていくから心配しないでね」
柩の蓋を閉じるときは、何かを抑えるように、女性は普段着の笑顔を取り戻していた。
ただ、濡れてシワくちゃになったエプロンだけが、女性の人柄と心情を映し出していた。
それから後、飼い主を失った猫達がどうなったのかは知らない。
きっとまた、女性も猫達も元気に自分達の世界をうまく渡っているのだろう。
これを書いている特掃野郎は、風体は野良猫・実態は飼い猫。
目に見えないものを信じながら、苦しみ多き人生を奮闘中。
そして、少しでもうまく世の中を渡れるよう頑張っているのである。