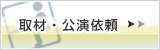特殊清掃を扱う専門会社「特殊清掃24時」:特殊清掃「戦う男たち」2007年分
特殊清掃「戦う男たち」
あったかぞく(後編)
仕事のせいか、もともとの性質か、私は毎日のように自分の死を考える。
日よっては恐怖し、また日によっては安堵しながら。
それと同時に、生きることの不思議さと夢幻性を強く感じる。
考えれば考えるほど、目に見えていること・耳に聞こえること・肌で感じること全てが夢や幻のように思えてくる。
・・・生きていることって、本当に不思議なことだ。
人が死ぬ確率は100%
それを証すかのように、毎日毎日、何人もの人が亡くなっている。
日本だけでも毎日何千人もの人が。
そして、それを待つ死人予備軍には、自分自身や身近な人達が含まれていることも紛れもない事実。
それをどう受け入れて消化するか、人生の課題である。
「まず、暖房を止めて、部屋の空気を換気してからにしましょうか」
私は、故人の着衣の着替作業に入る前に、部屋にこもった空気を入れ換えることを提案。
遺族に暖房を止めてもらい部屋の窓を全開にすると、暗い外から冷たい風が一気に通り、部屋中に充満していた生暖かい悪臭はたちどころに一掃された。
「これからは暖房はつけないで下さいね」
部屋の窓を閉めながら、私は念を押した。
それに対する遺族の反応は鈍く、故人の死を受け入れたくない心情を伺わせた。
「私はここで待っていますから、必要であれば声を掛けて下さい・・・お手伝いしますから」
亡くなっているとはいえ、女性の着替えを見物している訳にもいかないので、私は、故人の姿が見えない位置、隣の部屋の襖の陰に正座して待つことにした。
決まった規則があるわけではないのだろうが、病院で亡くなったほとんどの遺体は、白地に紺模様の浴衣を着せられている。
脱着がしやすくて入院療養には便利なのかもしれないけど、見た目はかなりさえない。
しかも、この故人の浴衣は自らの腐敗体液で汚れていたので、きれいなものに着せ替えたがる遺族の気持ちは充分に理解できるものだった。
「10~15分程度で終わるだろう」
そう思いながら畳の上に座り、私は、襖の向こうから聞こえる女性達の話し声に耳を傾けながら作業が終わるのを待った。
〝着衣の着せ替え〟と言っても、それが遺体となると簡単にはいかない。
遺体は、亡くなった直後から腐敗を進めていくことは前記したが、同時に外気温に合わせて体温が下がり、死後硬直が始まる。
しかも、寝たきりの姿勢で。
そんな遺体は、身を起こしてくれるわけでもなく、腕を曲げてくれるわけでもない。
手の指一本動かしてくれない。
そんな遺体の着衣を着せ替えることが簡単にはいかないことは、容易に想像してもらえることだろう。
この遺族にとっても、やはり難しい作業のようで、襖の向こうから聞こえてくる話し声からは、女性達の作業が難航していることが想像された。
しかし、私は〝声を掛けられてもいないのにしゃしゃり出るのは、余計なお節介〟と判断して、黙って座ったままでいた。
結果的にその判断は正しかった。
当初、私が予想していた時間ははるかにオーバーしたけど、パジャマへの着せ替えを自分達の手だけでやれたことに遺族は満足そうだった。
そしてまた、きれいなパジャマ姿になった故人も、嬉しそうに微笑んでいるようにもみえた。
「きれいに着せ替えができてよかったですね」
「はい・・・」
「では、ドライアイスをあてさせていただきますね」
「・・・」
やはり、二人の女性は、故人の身体にドライアイスをあてることに強い抵抗感があるようで、私の言葉に返事もせず黙り込んでしまった。
愛する者の死は、どの段階で受容されるものなのだろう・・・。
それは、人それぞれに異なるものなのだろうが、少なくとも、その時点での遺族は故人の死を受け入れることを拒んでいた。
そのうち、女性は
「髪をとかしてあげたい」
「お化粧をしてあげたい」
「冷やすのは(ドライアイスをあてるのは)それからにして欲しい」
と言い始めた。
それを聞いた私は少々困惑。
いつまでも先延ばしにしても、遺体の腐敗が進むばかりで、故人が生き返るわけではない。
そして、遺体の腐敗は遺族が望むことでもないはず。
が、乗り掛かった舟・・・
「この娘さん達にとっては母親の死を受容するために必要なプロセスかもな・・・」
と考えて、女性の申し出を了承した。
すると、二人の女性は嬉しそうに化粧道具を持ってきて、故人の顔にメイクを始めた。
髪の毛に至っては、ブラシでとかすだけではなくドライヤーでブローまで・・・できなかった親孝行を果たすかのように丁寧に・丁寧に。
その姿は、無邪気に母親と遊ぶ子供のように、また母親に甘えている子供のようにも映った。
そしてまた、
「母親の死を受け入れたくない」
「別れが名残惜しくて仕方がない」
という心痛がストレートに伝わってきた。
「生まれ変わっても、またお父さんと結婚してね」
「そして、私達を産んでね」
「また同じ家族で、仲良くしようね」
私は、〝生まれ変わり〟等というものは信じてはいない。
だけど、楽しそうに話しす二人の女性と照れ臭そうに微笑んでいる男性を見ていると、〝ホントにそうなれたらいいね〟と、自然に思わされるのだった。
暖房を止めた部屋は、少しずつ肌寒くなっていたけど、そこには家族の温もりがあった。
その温もりは、冷酷な死をもあたたかいものに変えていく力がありそうに思えて、何となくホッとするものがあった。
「お待たせしてすいません」
部屋の隅で地蔵になっていた私に、男性は気を使ってくれた。
それでも、〝娘達には思い通りにさせてやりたい〟〝妻もそれを望んでいる〟といった男性の思いが伝わってきて、〝大丈夫!全然平気です〟という表情で頷く私だった。
それから、しばらくの時間が経過。
もともと正座は不得意ではないはずなのに、私の足はだいぶ痺れていた。
そんな中、次第に冷えて硬くなってくる故人を前にしては、否応なくその死を受け入れざるを得なかったのだろう、それまでは涙を流すような気配はまるでなかった三人は、急にシンミリと泣き始めた。
「ドライアイスをあてる前に、家族だけの時間をつくってあげた方がよさそうだな」
足の痺れを解すためもあり、私は一旦外に出て小休止することにした。
「あ~ぁ・・・また一人死んじゃったんだなぁ・・・」
玄関を出た私は、いつものように空を仰いで深呼吸。
外の空気は冷たかったけど、星空に向かってどこまでも澄んでいた。
そして、家の中から聞こえる家族の泣き声に、必然の死に向かいながらも奇跡的に生きている今を噛み締める私だった。