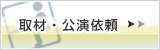特殊清掃を扱う専門会社「特殊清掃24時」:特殊清掃「戦う男たち」2007年分
特殊清掃「戦う男たち」
のんだくれ(後編)
「ん゛ー、このニオイ、たまんないなぁ」
私は、慣れるに慣れない刺激的な香りに、進めかけた足を一時停止。
家の中はシーンの静まりかえり、人気のない薄暗さが私の緊張感を刺激してきた。
雑然とした室内は、この家が男性の一人所帯だったことを伝え、台所やリビングに転がる空缶・酒ボトルは故人の荒れた生活ぶりを示唆。
私は、散乱するゴミを横目に目当ての部屋へ向かった。
向かったのは二階の寝室、故人が倒れていたとされる部屋。
私の登場に驚いたのだろう、それまで静かに潜んでいたハエが一勢に飛行乱舞。
ハエの唸るような羽音は、私を脅すかのごとく耳に響鳴。
その不気味な重低音は、慣れた私でも鳥肌が立ちそうになるくらいだった。
それでも、私はハエが直接的に襲ってくるのもではないことを知っていたので、彼等には目もくれず窓に向かって直進。
そして、暗闇に明かりを入れるため、カーテンを一気にスライド。
と同時に、ザラザラザラザラ・・・と、無数の黒粒が床に落下。
窓辺には、外への脱出を望みながら息絶えたハエが無数に重なり合っており、その黒山がカーテンに連られて崩れたのだった。
それはまた、外の光に反射する緑色の黒体は、この部屋で起こった出来事を証言しているようでもあった。
「最期は苦しかったのかな・・・」
汚染は、ベッドと下の畳に半々に浸透。
その不自然な形状と畳に貼り着いた大量の頭髪が、故人の最期の苦しみを連想させた。
中の見分を終えて出ると、依頼者は近所の人と外で立ち話。
もうこの家に戻り住むつもりはないからだろうか、世間体を気にする様子もなく、近所の人達とも和気あいあいと会話。
近所の人達に溶け込んだその姿は、とてもこの家の当事者のようには映らなかった。
依頼者は故人の妻、中年の女性。
数ヶ月前まで、現場の家で故人と暮らしていた。
不自然な明るさの中に隠れた憔悴感があり、それは女性と故人との間に並々ならぬ事情があったことを表していた。
しかし、過去のことを掘り返して家が片付くわけではない。
私は余計な質問はせず、中の状況と必要作業の説明に徹した。
腐乱死体現場の凄惨さは警察官もよくわかっている。
だから、特掃の依頼者には、警察から「現場には立ち入らない方がいい」と言われている人も多い。
もちろん、これは〝強制〟ではなく〝任意〟なのだが。
この女性も同様のことを警察から言われており、それに従っていた。
現場の部屋を見てきた私も、女性が部屋を見ることには賛成できなかった。
私にとってはミドル級であっても、女性にとっては無差別級。
後々の人生を考えるとリスクが高すぎて、安易に見せられるものではなかった。
それでも女性は、中から持ち出したいモノがあるようで少し困った様子をみせた。
「代わりに見てきましょうか?」
「え?いいんですか?」
「どうせ、(身体に)ニオイも着いちゃってますし、そのくらい大丈夫ですよ」
「たいしたモノじゃないんですけど・・・すみません」
数ヶ月前まで暮らしていただけあって、女性は、部屋の模様や家財・生活用品の置場所をほぼ正確に記憶。
私は、紙に見取図を書いてもらい、それにもとづいて女性から頼まれたものを探して搬出。
女性が持ちだしたがっていたものは、手紙・写真・置物etc・・・この家の、この家族の思い出の品々。
てっきり金目のモノだとばかり思っていた私は、運び出したモノを見て、内心でバツの悪い思いをした。
それから、私達は外でこれからのことを打ち合わせ。
始めの話題は作業のことに集中していたものの、話しているうちに打ち解けてきて、話の内容は生前の故人についてのことに変わってきた。
「病気で死ぬか自殺で死ぬか・・・そう長くは生きないだろう・・・はじめからそう思ってました」
女性は、肩の荷が降りたような穏やかな表情を浮かべ、静かに話し始めた。
故人は、若い頃からの酒好き。
飲む量は少なくなかったけど、酒癖が悪いわけでもなく人に迷惑をかけることもなし。
また、他に趣味らしい趣味もなく娯楽らしい娯楽も持たず、仕事も真面目。
生活費を圧迫するほどでもなかったため女性も容認。
しかし、ある時の健康診断で血糖値の異常を発見。
その時はまだ、糖尿病の一歩手前の状態だった。
はじめのうちは食事療法と運動の励行で療養。
しかし、飲む酒の量はなかなか減らすことができず。
そのせいもあって、病気は日に日に進行。
そのうちに完全な糖尿病になり、薬が処方されるようになった。
そうなると、禁酒はもちろん食事制限も厳しくなる一方。
しかし、いくら節制しても病状は回復するどころか悪化の一途をたどるばかり。
我慢してばかりの生活がバカバカしくなった故人は、自分で勝手に酒を解禁。
健康だった頃に比べて量は抑えてはいたものの、晩酌は再び日常的なものに。
当然のことながら病状は急速に悪化。
入退院を繰り返す中で、とうとう仕事にも支障をきたすような身体になってしまった。
仕事を失ったのを契機に、故人の精神と生活ぶり一段と荒廃。
朝昼かまわす飲むようになり、量も増加。
そして、もともとは悪くなかったはずの酒癖も悪くなり、酔うとキレるように。
それでも、家族は耐えた。
しかし、故人が暴力をふるうようになってから、アッケなく家族は崩壊。
女性は、子供を連れてこの家を出て行ったのだった。
「〝酒も飲めないくらいなら野垂れ死んだ方がマシだ!〟って本人は言ってましたから・・・ホントにそうなって本望かもしれませんね・・・」
女性は、何かを達観したかのような笑みを浮かべながら話を続けた。
「ところで、貴方はお酒を飲みますか?」
「・・・はい」
「それは付き合いで?それとも好きで?」
「・・・好きで・・・」
「そお・・・悪いことは言わないから、やめた方がいいですよ」
「はぁ・・・」
「今のうちからやめておかないと、後からなんて絶対にやめられませんから」
「はい・・・」
「お酒って、楽しいものだと思ったら大間違い!本当は恐いものなんですよ」
「おぼえておきます」
「私には娘が二人いるんですけど、お酒を飲む男とは絶対に結婚させないつもりなんです」
「・・・」
「絶対にね!」
「・・・」
「私と同じ苦労はさせたくないですから」
「・・・」
「夫は、悪い人じゃなかったんです・・・お酒に負けちゃっただけなんですよね・・・」
「・・・」
女性は、家から持ち出したモノを大事そうに眺めながら、私を諭すように、そしてまた亡き夫に訴えるように呟いた。
色んな想いが混ざりあってたであろう女性の言葉に、私は、言葉を失くしたまま立ち尽くすだけだった。
耳の痛い話は身のためになる。
自らは発することができない重い意味があるから。
故人が抱えた痛みと女性が抱える痛みを想いながら、当夜の晩酌をどうするか真剣に悩む私だった。