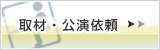特殊清掃を扱う専門会社「特殊清掃24時」:特殊清掃「戦う男たち」2007年分
特殊清掃「戦う男たち」
親の愛、子の哀
親が子を虐待する、親が子を捨てる、親が子を殺す・・・
世間の情報に疎い私の耳にも、そんな殺伐としたニュースは入ってくる。
そんな人間(親)には、強い嫌悪感や憤りの感情を覚えると同時に、人間が抱える陰の本性をみるような気がして、どうにも暗い気分になる。
その反面、私の仕事には、親の愛に気づかされる場面も多い。
「子供のためだったら死ねる」と言う親の姿を見るときだ。
人のために命を捧げるなんてことは、普通はできないこと。
それができるのは、余程のできた人間くらいだろう。
しかし、「自分の子供のためだったら・・・」と思う親は多いのではないだろうか。
それは、特段の人格者や偉人というわけではなく、ごく普通の人。
そんな人(親)には、強い敬意と憧れの感情を覚えると同時に、人間が抱える陽の本性をみるような気がして、気持ちが熱いくなる。
〝人のために自分の命をも惜しまない〟
そんな利他愛は、人間が持ち得る究極の愛かもしれない。
そして、自分以上に子供を愛する親の心に、究極の愛が宿るのかもしれないと思う。
人は、とてつもなく愛情深い生き物にもなれれば、とてつもなく冷酷な生き物にもなれる。
人は誰しも、心の中に愛と悪の種を両方持っている。
人それぞれに芽の出し方が違うだけで、それは誰の心にもあるものだと思う。
それは、この私にも言えること。
人の善行を敬うことはいいにしても、人の悪行を一方的に非難できる資格が自分にあるのかどうかを自問する。
そうすると、自分が、人を軽々と非難できるような善人ではないことに気がつく。
そして、自愛と自己嫌悪の間を行き来しながら、目指すゴールに向かって前進しようと試みる。
「代われるものなら代わってやりたかった・・・」
故人の母親は、そう言いながら遺体に泣きすがった。
そして、その傍らでは、故人の父親・女性の夫らしき男性が、泣きすがる女性を支えながら固い表情を浮かべていた。
「ホント、〝身代わりになってやりたい〟と何度思ったことか・・・」
誰に言うわけでもなく、男性もそう呟いていた。
亡くなったのは若い男性。
異様に痩せた身体と似合わないニット帽が、長い闘病生活を物語っていた。
故人は、その昔に小児癌を患ったことがあった。
一旦は治ったものの、その後遺症は残った。
後遺症に悩まされながらも、普通の生活を取り戻せた幸運に感謝しながら成長。
本人も家族も、そのまま何も起こらないことを願い、何も起こらない人生をイメージしていた。
しかし、成人になって間もなく癌は再発。
長い苦闘を経てその日を迎えたのだった。
「元気な身体に生んでやれなくてゴメンね」
「苦しむために生まれてきたようなものだったね」
冷たくなった息子を前にして、その生涯と死を消化できずに苦悩する両親の姿は、重い何かを痛切に訴えかけてきた。
両親は、故人を苦しみから解放してやることはできなかった。
しかし、故人と苦悩と痛みを共有した親の愛は、故人に伝わっていただろう。
そして、平均寿命より短かった人生、平均的な幸せさえ手に入れることができなかったかもしれない人生だけど、故人が二人の子として生きてきたことは決して無意味なことではないと思った。
故人の柩の中には、色々なものが入れられた。
洋服・本・写真・手紙・お菓子・・・可愛がっていた動物のぬいぐるみも。
成人男子がぬいぐるみを可愛がっていた様は少々の違和感を覚えさせたが、「死に対する孤独感を紛らわすためのに必要だったのかも・・・」と思うと奇異に思う気持ちはなくなった。
柩の蓋を閉めるとき、両親は号泣。
もらい泣きをするほどの純真さはとっくに失くしている私だったが、その負の迫力は、私の目さえも潤ませるほどだった。
また、その場の悲哀は例えようもなく辛いものではあったけど、子を想う親の姿にはホッとするような何かがあった。
また、別の現場。
周囲を田畑に囲まれて、その家は建っていた。
家には大勢の人が集まっており、それは親類縁者だけではなく、近所の人達も混ざっているようだった。
故人は老年の男性。
遺体の死後処置を終えて納棺を始める段階になると、部屋には入りきれないくらいの人が集合。
ガヤガヤと騒々しい人達には故人の死を悼む悲哀感も見受けられず、逆に、祭のような活気すら感じるくらいだった。
なにも、葬式だからと言って暗く辛気臭くしていないといけないわけではない。
明るい雰囲気で活気があったっても悪くないと思う。
私は、場の雰囲気に気持ちの波長を合わせながら作業を進めた。
「変な話なんですけど・・・」
中年の女性が話し掛けてきた。
その人は、故人の娘らしく、私に何かを尋ねたそうだった。
「(柩に)何か入れた方がいいんじゃないですか?」
「え?」
「人形とか、ぬいぐるみとか・・・」
「はぁ・・・」
「(アノ世に)一緒に連れていかれないための身代わりで・・・」
「身代わり・・・」
「普通は入れませんか?」
「私もこの仕事を随分やっていますけど、あまり経験ないですね」
「そうですか・・・」
「あと・・・個人的な考えなので責任は持てませんが・・・」
「はい・・・」
「亡くなった人が生きている人を道連れにしたり死に追いやったりるようなことはないと思いますよ」
「そうですか・・・」
「この類のことは、私は全く気にしませんが・・・ただ、皆さんが気になるようだったら安心できるようになさっていいと思いますよ」
「んー・・・」」
実際に、〝身代わり人形〟を柩に入れる習慣のある地域もあるらしい。
この女性にもその知識があり、顔は真剣そのもの。
自分達の誰かがアノ世に連れて行かれないように、策を打っておきたいみたいだった。
結局、家に置いてあった適当な人形が柩に納められた。
そうされる故人がどういう心境か興味深いところだったが、それは知る由のないこと。
ま、それで遺族の不安が少しでも解消されれば、それでヨシといったところだろう。
死を恐れる気持ちが強ければ強いほど、それにまつわる迷信は人の心に刻まれやすい。
友引に葬式をやらないことや葬式に行ったあとに身体に塩をふることは、その代表的なものだろう。
〝死〟は、そこまで人を恐れさせる絶対的なパワーがある。
しかし、どんなにあがいたって人には死から逃れる術もないし死に対する力もない。
イヤでも受け入れるしかない。
しかし、人は死んでもその愛は代々に伝えられて絶えないものかもしれない。
さしづめ、〝人は死んでも愛は残る〟と言ったところか。
↑「我ながら、いいことを言うなぁ」
〝人が生きる意味〟〝人が死ぬ意味〟を想いながら、携帯片手に樮笑んでいる私である。