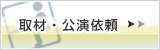特殊清掃を扱う専門会社「特殊清掃24時」:特殊清掃「戦う男たち」2008年分
特殊清掃「戦う男たち」
老いの先(前編)
遺品処理の問い合わせが入った。
会社から連絡があり、外現場にいた私は手が空くのを見計らって依頼主に電話を入れた。
「あれ?留守かな?」
しばらく鳴らしても、誰も電話にでず。
忙しかった私は、しばらくしてかけ直すことにして電話を切った。
それからまた一仕事をこなし、手が空いたところで再び電話。
すると、今度はすぐに年配の男性がでた。
その声は弱々しく、舌もうまく動いていないよう。
男性がかなりの高齢であると踏んだ私は、意識して声を大きくし、ゆっくりと喋った。
「もしもし・・・〓〓さんですか?」
「はい・・・そうです」
「遺品処理の件でお電話したんですけど」
「はいはい・・・少し前に電話くれたのはアナタですか?」
「はい・・・かけました」
「忙しいのに、ごめんなさいね」
「?」
「脚が悪くてねぇ・・・すぐにでられなかったんですよ」
「いえいえ、とんでもないです・・・こちらこそ、もう少し待ってればよかったですね」
私は、男性の気遣いに恐縮。
同時に、自由のきかない身体で急いで電話にでようとした姿を思い浮かべて、何だか申し訳ないような気持ちになった。
「ところで、荷物の量はどれくらいありますか?」
「長く暮らしていましたから、結構ありますよ」
「そうですか・・・できたら、一度、お宅に伺わせていただきたいのですが・・・」
「あぁ、構いませんよ」
「ご都合はいかがですか?」
「家にはずっといますから、いつでもどうぞ」
「そうですか・・・では、ちょっと先になりますけど、〓日の〓時はいかがでしょう」
「いいですよ・・・玄関の鍵は開いてるので、勝手にあがってきて下さい」
〝百聞は一見にしかず〟
高齢の男性にアレコレと質問して頭を悩ませるより、直接、現場を見た方がいいと思った私は、日をあらためて訪問することにした。
約束の日時。
現場は公営の大規模団地。
団地内の案内図も複雑で、男性宅を探すのも一苦労。
方向音痴の私は、建物の位置を念入りに頭に叩き込み、進むべき方向を指差しながら現場に向かった。
目的の建物に着いた私は、一階の集合ポストに男性宅の番号を探した。
そして、ポストの名前で棟が間違っていないことを確認してから、エレベーターに乗り込んだ。
それから、長い通路を歩き、やっと男性宅前に到着。
更に、表札に書かれた名前を見て、そこが目的の家に間違いないことを確認した。
インターフォンはあったが、それには〝ご用の方は玄関にお入り下さい〟との貼り紙。
「いきなり玄関?ちょっと不用心じゃない?」
と思いながらも、
「玄関の鍵は開いてるので、勝手にあがってきて下さい」
と言っていた男性の言葉を思い出し、私は部屋番号と表札を再確認。
それから、ドアノブに手をかけた。
ドアをゆっくり引くと、話の通り、鍵はかかっておらず。
私は、少し開けて頭だけ中に入れた。
「ごめんくださ~い」
私は、室内に向かって、小さく声をかけてみた。
しかし、シーンと静まる部屋からは反応はなく、私の声が響くのみ。
「ごめんくださ~い!」人の家の玄関を勝手に開けて覗く行為は、なかなかの抵抗感を覚えるもの。
私は、その気マズさが嫌で、二度目の声は大きくしてみた。
「は~ぃ」
すると、部屋の奥の方から誰かが応答。
男性が返事をしてくれたみたいだった。
私は、首だけ玄関に突っ込んだまま、名を名乗り要件を伝えた。
すると、男性は、部屋にあがるよう案内。
私は、これまた大きな声で挨拶をしながら部屋に上がった。
「失礼します・・・こんにちは」
「お待ちしてましたよ」
男性は、想像通り見るからに高齢者。
台所の椅子に腰掛けたまま、にこやかに私を迎えてくれた。
そして、キャスター付の椅子を車椅子のように使って、私と話しやすい位置に寄ってきた。
「座ったままですいませんね」
「いえいえ」
「最近、足腰が弱まってきたものですから」
「それは大変ですね」
「歳には勝てませんなー」
男性は、〝身体の衰えも自然のこと〟と素直に受け入れているようで、穏やかに笑っていた。
「早速ですけど、片付けたい荷物は、どの辺りのものですか?」
「この家にあるもの全部です」
「え!?全部ですか?」
「えぇ・・・子供達が、欲しいものがあれば少しは持ち出すかもしれませんけど、ほとんどのものを処分することになるお思います」
「〝どなたかの遺品〟って伺ってるんですけど・・・どなたの遺品なんですか?」
「死んだ女房のものもありますけどね」
「はい・・・」
「お願いしたいのは、私の物も含めた遺品処理なんです」
「・・・」
男性は、亡くなった妻が残した荷物を片付けるついでに、自分の死後始末の段取りをつけようとしていた。
高齢者で、自分の死んだ後の始末を考えている人は案外と多いので、話を聞いた私も大して驚かず。
むしろ、男性の温和な雰囲気もあいまって好感と共感を覚えるくらいだった。
「私も、ご覧の通りの年でしょ」
「はぃ・・・」
「先は短いですよ」
「はぁ・・・」
「だから、今のうちに片付けの段取りをつけとこうと思いましてね」
「はい・・・」
高齢者や病人に死を語ることはタブー視されやすい。
また、それを話すことや聞くことに嫌悪感を覚える人も多いだろう。
しかし、この男性にそんな気遣いは全くいらなそうだった。
「子や孫には迷惑をかけたくないですからね」
「はい・・・」
「そうは言っても、死んだ後じゃ何もできないじゃないですか」
「そうですね」
「だから、今のうちにやっておきたいわけなんです」
「なるほど・・・」
「でも、そう言うわけですから、片付ける日がいつになるかわからないんですよ」
「・・・ですよね」
「こんなんじゃ、仕事になりませんか?」
「いえいえ、そんなことはありませんよ」
自分の死を考えることは、寂しく怖いものかもしれないけど、それだけではなく、思いもよらない意義と新しい気づきを与えてくれるもの。
決して無意味なことではない。
私は内心で、男性の考えに大きく頷いた。
もともと年配者と話をするのが好きな私は、未調教の野次馬にならないように気をつけながら色々と質問。
そんな私を、〝話の合いそうな男だ〟と思ってくれたのか、男性も嫌な顔ひとつせず、プライベートな話を色々と聞かせてくれた。
男性の年齢は90台前半。
年金生活をするようになったのを機に、この団地で暮らすようになった。
奥さんは先に亡くなっており、ここ数年は一人暮らし。
男手しかなくて不便なことも多かったけど、身の回りのことも全部自分でやってきた。
子や孫もいるが、それぞれの土地でそれぞれの生活。
たまに遊びに来たり電話がかかってくるだけで、お互いに負担を掛け合わない、良好な関係を維持していた。
経済的には、年金の範囲内でやりくり。
贅沢はできなくても、人並みの暮らしはできてきた。
そんな生活の中、加齢による身体の弱まりは進行。
80台後半なると介護ヘルパーの手をかりないと、簡単な衣食にも支障をきたすようになってきた。
そして、その依存度は年を追うごとに増していき、とうとう、歩行が困難になるくらいまで体力は低下。
私が訪問したときには、普通に立つこともままならない状態になっていたのだった。
「でも、これ以上、お一人で生活するのは厳しいんじゃないですか?」
「まぁね・・・でもねぇ、今更、住むところを変えたくないんですよ」
「はぁ・・・」
「できることなら、ここでポックリ逝ければいいんですがね」
私には、男性が一人で生活するのも、そろそろ限界にきているように思えた。
男性もまた、自分の一人暮らしが限界にきていることはもちろん、自分に残された時間が長くないことも悟っているようだった。
だから、私も、
「そんなこと言わずに、長生きして下さいよ」
「養生すれは、また元気になりますよ」
なんて、軽率なことを言うのはやめておいた。
私は、男性が望むように、本人がポックリと孤独死した様を思い浮かべてみた。
しかし、私には、男性が思い描いているような安楽な光景は浮かんでこなかった。
それどころか、見慣れた例の光景ばかりが頭を過ぎって、それが私の気分を神妙にさせた。
「死ぬことは怖くないけど、長患いして苦しむのはイヤだね」
「そうですね・・・」
望み通り、長患いもせず住み慣れた我が家でポックリ逝くことは、本人にとってはいいかもしれない。
しかし、場合によっては残された人が長患いしてしまう可能性がある。
「〝部屋でポックリ死にたい〟なんて、気持ちはわかるけどお勧めはできないよなぁ・・・」
私は、内心でそう思った。
〝当然〟と言えば〝当然〟、〝普通〟と言えば〝普通〟なのだろうか・・・
男性の頭には、死んだ人の身体がどうなっていくかなんて、全くないみたいだった。
そして、男性同様、一般の人も、自分が死んだ後に残る身体については、あまり深くは考えないのかもしれない。
せいぜい、〝最期は何を着せてもらおうかな?〟などと考えるくらい。
あとは、〝遺骨はどうしようか〟などと思うくらいか。
やはり、自分の身体が腐っていく状況を想定している人は少ないだろう。
だから、自宅でポックリ逝くことを安易に?望むのかも。
まぁ、その志向自体が悪いわけではないのだが、残念ながら、現実はそう簡単でなかったりするのだ。
部屋の観察と一通りの話を終えた私は、現場から引き揚げることに。
「見積書は会社に帰ってからつくりますから」
「はい、お願いします」
「でき上がったら、お知らせしますので」
「はい・・・鍵はずっと開けっ放しですから、必要があったら、いつでも来て下さい」
「はい・・・でも、鍵を開けっ放しじゃ不用心じゃないですか?」
「平気ですよ・・・鍵をかけたり開けたりするだけでも大変なんでね」
「最近、物騒ですから、気をつけて下さいね」
「な~に、盗みたいものがあれば好きなだけ盗ませればいいですよ」
男性は、何かを達観したような穏やかな笑顔を浮かべた。
その笑顔に見送られながら、私は現場を後にした。
内容にもよるけど、現場作成でない場合の見積書は郵便・FAX・E-mailを使って送ることが多い。
この男性にはFAXもE-mailもなかったので、郵送することに。
そして、その前に、〝金額だけでも伝えておこう〟と男性に電話をかけた。
「でないなぁ・・・」
私は、ゆっくりとした動作で電話にでようとしている男性の姿を想像して、長めに鳴らし続けた。
しかし、いつまて鳴らしても男性はでず。
「出掛けてる?・・・わけないよなぁ・・・」
受話器から聞こえる呼び出し音を聞きながら、私は怪訝に思った。
そのうちに、私の頭は、イヤなことを想像し始めた。
「もしかして・・・」
マイナス思考が染みついている私の頭には、ぼんやりと陰鬱な画が浮かんできた。
そして、そのうちに、それはリアルな光景に変わってきた。
「ちょっと、行ってくるか!」
私は、妙な胸騒ぎを抱えながら、男性宅に向かって車を走らせた。
つづく