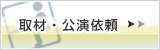特殊清掃を扱う専門会社「特殊清掃24時」:特殊清掃「戦う男たち」2008年分
特殊清掃「戦う男たち」
老いの先(後編)
「気が急くなぁ・・・」
そんなときは、赤信号や渋滞がやたらと多く感じるもの。
ハンドルを握る手は汗ばみ、外を見る視線は泳ぎ・・・
電話にでないくらいで死んでる可能性を憂うのは私ならではの思考傾向かもしれないけど、私の頭には男性が部屋で冷たくなっている光景が駆け巡っていた。
一日おきにヘルパーが来てるはずだから、普通に考えると、亡くなっていたとしても2日以内には発見されるはず。
夏場の2日なら、まったく油断はできないが、幸い?そのときの季節は冬。
遺体が大きく損壊している可能性は低いと思われた。
ただ、冬場でも、暖房が大きな影響を与えることがある。
とりわけ、コタツ・ホットカーペット・電気毛布が与えるダメージは大きい。
コタツに入ったままで、上半身は何倍にも膨れ上がり、下半身はミイラ状態になった遺体・・・
ホットカーペットの上で、焼汁が流れ出した遺体・・・
電気毛布にくるまれて、発酵していた遺体・・・
私は、脳裏に焼き付けていた男性宅の模様を慎重思い出し、男性が使っていた暖房器具を記憶の中に探した。
「確か・・・エアコンと電気ストーブを使ってたな」
男性が電気毛布を使っていたかどうか定かではなかったが、コタツとホットカーペットはなかったように思った私は、ひとまず安堵。
そんなことで安心している場合ではないのだろうが、とりあえず一息ついた。
「一人で風呂に入れないはずだから、汚腐呂にはなってないな・・・」
「トイレもポータブルだから、汚手荒になってることもないだろうな・・・」
「やっぱ、ベッドかな・・・」
暖房の次は、倒れている場所を推測。
私には、安否を確認する前から男性を殺してかかることに問題があることに気づく余裕はなかった。
そんなことを考えていると、男性宅への道程がやたらと長く感じた。
時折、苛立ちを覚えながらも、とにかく、私は冬の街を駆け抜けた。
初めて訪問したときは、団地内の要領がわからずに色々と手間取った私だったが、二度目その時は〝勝手知ったる我が家〟のごとく、迷うことなく部屋に直行。
走ったせいか緊張のせいか、玄関前に立つ私の心臓はドッキンドッキンと波打ち、呼吸はハッハッと小さく刻まれていた。
「もし亡くなってたら、俺も一緒に警察行だな・・・」
第一発見者が疑われることは承知のうえ。
私は、躊躇う気持ちを抑えながら、ドアノブに手をかけた。
「あ!開いてる・・・」
前回同様、ドアに鍵はかかっておらず。
と言うことは、〝男性は中に居る〟ということ。
私は、恐る恐るドアを引いた。
「ご、ごめんくださ~い」
私は、微妙に震える声で挨拶。
同時に、小刻みに鼻で空気を吸った。
しかし、緊張のあまり臭覚は麻痺。
部屋に異臭があるかどうか感知することはできなかった。
「入ってみようかな・・・」
呼び掛けに対して反応のない部屋に若干の恐怖感を覚えながら、勝手に中に入っていいものかどうか迷った。
住居不法侵入・窃盗容疑・殺人容疑・・・
マズいことばかりが頭を巡り、私はその場に硬直してしまった。
「ゴホン!ゴホン!」
少しすると、中から物音が。
よく聞くと、男性が咳き込んでいるようだった。
「ん?生きてる?」
中から聞こえるそれは人の声・・・
間違いなく男性が発しているものだった。
「よかったぁ~」
〝胸を撫で下ろす〟とはまさにこのこと。
私は、心臓と肺を労うように、胸をさすった。
「こんにちは~!失礼しま~す!」
私は、男性に確実に届くくらいの大きな声で挨拶。
一呼吸ついてから玄関を上がった。
男性は、奥の和室のベッドにいた。
昼間なのにカーテンは閉められ、部屋は薄暗く、湿っぽい空気が充満。
私の姿を見ると、横になったまま手を上げて笑顔をみせた。
「風邪でもひかれましたか?」
「いやいや、もともと肺が悪くてね・・・」
「〝肺〟ですか・・・」
「結核とかじゃないから、うつる心配はないですよ」
「大丈夫です、そんな心配はしてませんから・・・しかし、他のことを心配してましたよ」
男性は、言葉の後先に、風邪でもひいたような咳をついていた。
会話は普通にできてもベッドから起き上がろうとしないところから、男性が著しく体調を崩していることが伺い知れた。
「何度か電話したんですけど、でられないものですから・・・」
「電話?」
「はい・・・」
「かかってきてたかなぁ・・・」
男性は、枕元に置いてある小機を手に取って不思議そうな顔。
私は、携帯を取り出して男性宅の電話番号を照会した。
「合ってますねぇ・・・」
番号に間違いはなかった。
しかし、気になった私は、そのままダイヤルを発信した。
「ん?かかってるのかな?」
携帯からの呼び出し音は聞こえるものの、家電は静かなまま。
その代わりに液晶部分とダイヤルボタンがピカピカと点滅した。
「かかってるみたいですけど、呼び出し音が鳴りませんねぇ・・・」
携帯と家電を交互に見比べ怪訝な顔をする私を見て、男性は笑った。
そして、その理由を私に話してくれた。
電話機は、機能設定で呼び出し音が消されていた。
過去、寝ているところにどうでもいい電話が鳴って起こされて迷惑したことが何度もあり、それを避けるため、そうしているらしかった。
呼び出し音は鳴らなくても本体と小機がピカピカと光るものだから、それでも不便はなかったとのこと。
私が最初にかけた時も、既にそうなっていたみたいだった。
・・・と言うことは、眠っているときや電話機から離れたところにいるときは、かかってきた電話に気づくはずもない。
だから、私がかけた電話にでなかったことも頷けた。
「体調も優れないようですし、お一人でこれ以上は無理なんじゃないですか?」
「んー・・・」
「どなたかに連絡しましょうか?」
「今日は、ヘルパーさんが来る日だから、大丈夫ですよ」
「そうですか・・・」
力なく横たわる男性を前に、私は、お節介を焼くべきか慎むべきか迷うばかり。
片や、男性の方は身体は弱めながらも、精神は強く保っているようだった。
何はともあれ、男性が生きていたのは、私にとって幸いだった。
しかし、そんな男性を放って帰るわけにもいかず。
私は、介護ヘルパーが来る時間まで、男性宅に留まることにした。
「ヘルパーさんが来るまで、ここに居ていいですか?」
「私は構いませんけど、仕事の方は大丈夫ですか?」
「大丈夫です・・・これも仕事のうちですから」
「お金にならない仕事をさせて、申し訳ないですね」
「いえいえ、とんでもないです」
「でも、働けるうちは喜んで働いて下さいね」
「はい」
「稼いだお金はいずれ消えますけど、汗して働いたことはお金に換えられない宝になりますから」
「はい・・・憶えておきます」
会話を進めるうちに、男性は言葉に力を込めてきた。
そして、気のせいか、少し元気を取り戻してきたようにも思えた。
もともと、老人と話をするのが好きな私。
人生の先輩が聞かせてくれる証に、無駄な話はない。
そして、始めは慈愛で聞く話でも、結果的には自愛の話となって自分の人生に格別の収穫をもたらす。
私は、男性が発する言葉の一つ一つを重く受け止めた。
「それにしても、なかなかポックリとは逝かないもんですな」
「はぁ・・・」
「寝ていると、色んなことを想いますよ」
「そうですか・・・」
「特に、子供の頃や若かった頃のことは、何もかも懐かしく思い出しますね」
「・・・」
「でも、若い頃に戻りたいとは思いませんね」
「そうですか・・・」
「人生はね、一度しかないからいいんですよ」
「・・・」
「二度も三度もあったら、必死に生きないでしょ?」
「はい・・・」
「必死に生きてこそ、人生ってもんですよ」
「はい・・・」
「私は、死んだ父親の歳より十も長生きさせてもらいました」
「はい・・・」
「感謝なことです」
男性は、何かを悲観している風でもなくサバサバとした様子。
何かを達観したように、その表情は柔和そのものだった。
私と男性が、とりとめのない話に花を咲かせていると、予定の時刻になってヘルパーがやってきた。
いつまでも留まっていては邪魔になるばかり。
私は、あとはヘルパーにバトンタッチして、男性宅から退散することにした。
〝死〟・・・特に、自分の死を考えることは、とても有意義なことと私は考える。
もちろん、それで刹那的・短絡的になってはいけないのだが、深く深く考えると自然と神妙かつ厳粛な気持ちになってくるものだと思う。
こんな仕事をしている私は、普通の仕事をしていれば得られるものを得られていないかもしれない。
普通の仕事をしていれば、失わなくて済むものを失っているかもしれない。
(〝普通の仕事〟の定義は、かなり曖昧だけど)
しかし、死を考えるチャンスは、数え切れないくらい与えられている。
これは、何物にも換えられない宝かもしれない。
しかし、その死考は、この男性のように、死と直面し現実のこととして受け入れようとしている人に比べれば、リアルさに欠ける。
これだけ〝死〟にまみれていながら、どうしたって現実味に欠けているのだ。
それは、自らが歳をとったり大病を患ったりしないと、リアルに受け止めることができないものなのかもしれない。
ただ、この男性のような人と会って感情を移入すると、擬似的に自死を自分に近づけることができる。
それによって、薄暗い〝今〟が光に照らされ、人生に力が注ぎ込まれる。
そして、今を生きる力が湧いてくる。
「私、〓〓(男性の名)さんと会えて、よかったですよ」
帰り際、私はそう言って男性宅を後にした。
その時、私は、男性とは二度と会うことはないだろうと思っていた。
男性もまた、同じように思っていただろう。
男性は、痩せた顔に笑顔を浮かべて見送ってくれた。
後日、その後のことを担当のケアマネージャーが知らせてくれた・・・
男性は、一人暮らしは到底無理な状態に。
あの後、何日かのうちに、留まっていたかった家を出て病院に入院。
進退を繰り返しながら、日を追うごとに衰弱していった・・・
それから、程なくして、私は男性宅を片付けることになった。
公営とは言え賃貸住宅にかわりはなく、のんびりもしていられず。
知らせをしんみり噛み締める間もなく、作業の日程は慌ただしく組まれた。
季節は、寒い冬から暖かい春になっていた。
「笑って逝ったのかなぁ・・・」
空っぽになった部屋には、脳裏に焼き付いた記憶と、〝人生は一度しかないからいいんだ〟と言った男性の透明な笑顔が残るだけだった。