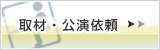特殊清掃を扱う専門会社「特殊清掃24時」:特殊清掃「戦う男たち」2009年分
特殊清掃「戦う男たち」
バスタイム(後編)
「この件は、まだ不動産屋に言ってないんですよ・・・」
「え!?不動産会社は、知らないんですか?」
「はい・・・言わない方がいいですよね?」
「ん?」
「そうしよ・・・そうします!」
「え?」
「もちろん、黙っててくれますよね!?」
「は?」
それを聞いた私は、その突拍子もない考えに意表を突かれ、言葉を詰まらせた。
実際、他にも、腐乱死体現場を秘密裏に処理し、何事もなかったかのように解約・退去したケースは複数ある。
そして、当初しばらくの間、不動産会社が気づかないでいることも。
しかし、事が公にならない可能性は極めて低い。
タイムラグはあれど、退去側の人間が想定できないことがキッカケとなって、明るみに出てしまうのだ。
まず、そのきっかけとなるのは、細部の汚染痕と残留する異臭。
きれいに消せると思って、一生懸命に掃除するのだろうが、所詮は素人の浅知恵。
汚染の程度にもよるが、遺体が明らかな腐乱レベルにある場合、並の掃除だけで現場を元通りにするのは不可能。
過去に書いた通り、私も、何度かこのケースに遭遇したことがあるが、やはり、どこもバレバレの状態だった。
仮に、物理的な原状回復が実現できても、それだけで事は収まらない。
遺体搬出作業は、何人もの警察官が来て騒々しくやることがほとんどなので、在宅の近隣住民がそれに気づかないはずはない。
そして、事が事だけに、その出来事は、人々の頭にハッキリと刻み込まれる。
ただ、近隣住民は、〝関わり合いになりたくない〟という気持ちで沈黙するだけで、口に戸を立てているわけではない。
だから、些細なことがきっかけでその口は開かれ、情報は漏れることとなる。
また、解約の申し出や引き渡しの際に、契約者本人が出てこないのも極めて不自然。
過去別件では、〝病気入院〟〝長期海外〟等と強引なことを言ったような人もいたが、聞く方(大家・不動産会社)からすると奇妙な話。
本人確認を求められては、シラを切り通せるものではない。
「いやぁ゛・・・それはちょっと・・・マズいと思いますが・・・」
「そうですか?」
「バレる可能性も高いですし、バレた時に、大変な問題になりますよ!」
「・・・」
「本件の類は、不動産契約の重要事項になるはずですし・・・」
「・・・」
「追求されて、〝知らぬ・存ぜぬ〟は、通用しませんからねぇ・・・」
「・・・」
「バレることを心配して、ビクビクしてるのもストレスかかりますよ」
「・・・」
「あと、〝バレる〟とか〝バレない〟とかの問題じゃないような気もしますし・・・」
「・・・」
特掃が終わった後のことを、女性がどうしようが請け負った仕事の範疇外。
〝あとのことは知ったこっちゃない!〟と、割り切れば済む話。
しかし、事前に相談されてしまうと話は変わってくる。
〝聞いた耳〟と〝話した口〟に相応の責任・・・
それが不可抗的行為としても、その片棒を担ぐことに責任が生じるような気がした。
同時に、それに対して抵抗感を覚えた。
「黙ってたことによって、事が大きくなったケースもたくさんあるんですよ」
「そう言われてもねぇ・・・」
「・・・」
「さっきおっしゃったようなことが、起こらないとも限らないじゃないですかぁ・・・」
「・・・まぁ・・・確かに、〝ない〟とは言い切れませんけど・・・」
「でしょ!?さすがに、そこまでは負担できませんよ・・・」
「・・・」
知ったかぶりの情報提供が、藪の蛇をつついたよう。
女性は、事実を明るみにすることによって強いられる可能性がある補償に対して完全に尻込み。
同時に、そこには、自信を持って女性を説得できない私もいた。
「不動産会社は、ホントに気づいてませんかね?」
「・・・と、思いますよ」
「ちょっとした騒ぎになったと思いますけど、近所の人が知らせた形跡もありませんか?」
「ないと思います・・・何の連絡もありませんから・・・」
聞けば、警察が来た時は相応の騒ぎになったとのこと。
それを、近所の人が気づいていない訳はなく。
それでも、その時点ではまだ沈黙は守られているようだった。
一方、女性も、故人の葬儀や現場の処理で頭がいっぱいで、不動産会社へ連絡することなど眼中になく。
私と話して、初めて不動産会社の存在に気づいたような状態だった。
「ところで、亡くなったのは、お身内の方ですか?」
「まぁ・・・」
「ご家族とか?」
「いや、まぁ・・・そんなところです・・・」
故人の氏名・死因・性別・年齢・女性との関係etc・・・
女性は、これらについてはあまり話したくなさそう。
険しく曇らせた表情に、〝その類のことは話したくので訊かないで!〟というメッセージを感じた私は、以降、この類のネタには触れないよう気をつけることにした。
「第一発見者は?」
「私です・・・」
「驚いたんじゃないですか?」
「そりゃもぉ!・・・ビックリしましよ!」
第一発見者は、女性。
浴室で変わり果てた姿になった故人は、どこからどう見ても生きているようには見えなかったが、気が動転した女性は、とっさに119番。
しかし、状況を聞いた消防署は「119番じゃなく110番へ」と返答。
何が何だか分からないまま、すぐに110番したのであった。
「どのくらい住んでられたんでしょう」
「一年くらいですね」
「賃貸契約の保証人は、どなたが?」
「私なんです・・・まさか、こんなことになるなんて・・・」
故人が、このマンションに暮らした期間は、一年足らず。
どういう経緯か知る由もなかったが、その賃貸借契約の保証人は女性。
後始末の責任から免れることができないことは、女性自身が一番よく分かっていた。
「嘘はいけませんが、不動産会社に、この状態は見せない方がいいと思いますよ」
「はぁ・・・」
「部屋の第一印象は、少しでもいい方がいいですから」
「はぃ・・・」
「できる限りきれいな状態にして、それから見てもらうことにしませんか?」
「はぃ・・・」
「私も、頑張って掃除しますから」
「わかりました・・・」
虚偽報告に反対した手前、私には暗黙の責任が発生。
私は、女性に家賃の延長負担を承知してもらい、作業日数を多めに確保。
工事抜きではなかなか難しい汚腐呂の原状回復を、特掃のみで実現することを目指して、その日のうちに特掃に着手した。
何日か後。
空になった部屋は、きれいそのもの。
故人が住んでいたのは一年足らずで、普通に生活していれば内装が著しく汚損するはずもなく、それは、当然・自然の状態。
大した掃除も必要なかった。
問題は浴室だったが、長い長いバスタイムを経た甲斐あって、ほぼ原状を回復。
それこそ、言わなければ誰も何も気づかないくらいの状態に戻った。
「ちょっと日数がかかりましたけど、ほぼ原状は回復できたと思いますよ」
「そうですね!お世話になりました!」
「この状態なら、相手(大家・不動産会社)のウケは悪くないはずです」
「ありがとうございます」
「あとは、事実をキチンと伝えることですね」
「はぃ・・・」
事実を伝えることに関し、女性は、力なく返事。
その視線は私の目から逸れ、空を泳いだ。
そして、その様子に寂しい疑心を抱きつつ、私は現場を後にしたのだった。
その日の夜。
風呂に入ると、色んな想いが頭を巡った。
「俺だったら、アノ風呂に入れっかなぁ・・・」
「最初は我慢が要りそうだけど、慣れれば大丈夫かな?・・・」
私は、自分が掃除した汚腐呂に〝入れる!〟と即断できないことを苦い笑みに換えて誤魔化した。
「あの人(女性)、(不動産屋に)ホントのこと言うかなぁ・・・」
「あそこで人が死んでたことは言っても、詳しいこと(腐乱溶解in浴槽)は言わないんじゃないかなぁ・・・」
別れ際に女性がみせた後ろめたそうな顔は、私に苦い疑念を引きずらせ、温まりかけた気分に水を差してきた。
「入浴中の酒は、身体に悪そうだなぁ・・・」
「でも、外にはない味わいがありそうだろうなぁ・・・」
答の出ない問いにのぼせそうになった私は、考えることを中断して風呂から上がった。
そして、至福の入浴中に亡くなった故人と後始末に苦慮した女性の心情を想いながら、苦いビールを飲んだのだった。